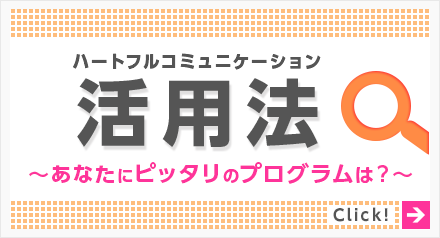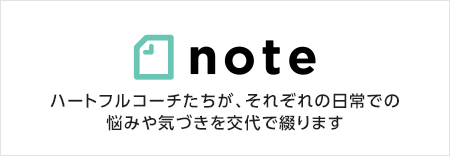「心配」は誰のため?
「心配」は誰のため?
東京の菅原典子です。
先日の敬老の日に、久々に実家に里帰りをしました。
いつもはネット注文のギフトと電話一本で済ませてしまう敬老の日ですが、暫くぶりに両親に顔でも見せようと思い立ち、家族で訪問を。短い滞在時間でしたが、皆で食事やケーキを楽しみ、サプライズのギフトに母も大喜び。父も孫との久々の再会に終始笑顔でした。そんな二人を見て、無理してでも行ってよかったと心から思いました。
昔からとても心配性でお世話好きな母。人情たっぷりの下町のお母さんといった感じ。
この日も、「心配」の二文字が何度か母の口から聞こえました。実は、私は母に心配されることがちょっと苦手で、話すのもちょっと面倒に感じていました。
2024年10月21日(月)
No.696
(日記)
長男とティッシュ〜お金じゃ解決できないのよね
石垣さんの続編、お待ちしてました! 石垣さんの対応と息子さんの行動、読みごたえがありました。
東京の平沢です。
今回は我が家の困った出来事から、気づいたことを切り取って綴りたいと思います。
洗濯物を取り出すと、またもやティッシュまみれ。「またか…」と思いながら、怒りがこみ上げてきました。大学4年生の長男がズボンのポケットにティッシュを入れたまま洗濯に出したからです。何度注意しても、同じことを繰り返す長男に、正直うんざりしていました。
「ポケットにティッシュを入れたまま洗濯に出さないでって言ったでしょ!」と怒りをぶつけても、長男は「あ、すまん」と一言で終わり。私はといえば、注意書きを貼ったり、ティッシュまみれの洗濯物を見せたり、理由を説明したりと、あれこれ試してみましたが、1ヶ月もするとまた同じことが起こるのです。
そんなある朝、出勤前の忙しい時間に、またしてもティッシュだらけの洗濯物を目にして、ついに私は「ティッシュをポケットに入れたまま洗濯に出した人には、500円の罰金を払ってもらいます!」と怒りの宣言をしました。夫や子どもたちは、私の怒りを前に黙って新しいルールを受け入れました。
2024年10月14日(月)
No.695
(日記)
親の覚悟
鈴木さんの日記は、同じ年頃の息子をもつ母親として通じること・参考になることが多く、子育てしていく勇気をもらいました。
石川県の石垣です。
前回は《子どもの巣立ち、その時私は…》で息子が塾に通い始めた時のことを書きました。今日は後日談で、自分に対する気づきと試してみたことを綴りたいと思います。
小6の息子が、市営バスで30分程の所にある塾へ通うことにも随分慣れたある日。バスの時間が迫っている中、2階の部屋に行ったきり降りてこない息子。今回のバスを逃すと、次のバスがギリギリ塾の開始に間に合う最終便。食事の支度をしながら私はソワソワしていました。
2024年10月07日(月)
No.694
(日記)
ママと息子の勉強タイム
子どもの幸せな自立を願い、子どもに任せて見守ろうとする決意。子どものことが大切だからこそ、自分が正しいと信じるところに従って口出ししたくなる親心。瀧澤さんの日記は私の心の葛藤を見るようです。
インドネシアの鈴木です。
暑かった日本での夏休み。今年は、息子の日本の学校デビューというイベントがありました。
息子も小学5年生になり、そろそろ将来自分がどこで、どういうふうに生きていきたいかを考えはじめる歳。日本人でありながら、日本を外から眺めることの多い息子には、日本の学校に行って、ほんの一面とはいえ日本の社会を自分の目で見て経験して欲しいと考えていました。
2024年09月30日(月)
No.693
(日記)
私ができること
タイの瀧澤です。
清瀬さんの日記を読みながら、私も子どもから自分が成長する様々な機会をもらっているなと感じました。「導くのではなく応援するスタンス」、これもまさに私に必要なこと。しっかり心に刻んで、日々の行動に活かそうと思いました。
先日、11歳の娘と寝る前に話しをしていた時のこと。
「昨日算数の宿題するのを忘れちゃって」「あら」「今朝、授業の前に急いでやった」「そうだったんだ」「だから、今日は忘れないように帰りのバスの中でやってきたの」「自分で忘れない方法を考えたのね」「うん」
という会話がかわされました。
自分の行動の結果を自分の責任として捉えて、改善策を考え対処できるように成長しているのだな、と娘の成長を嬉しく感じました。また、そんな彼女の話を受け止め、穏やかに会話できるようになっている自分の変化にも気づき、嬉しく思いました。
というのも、以前の私は、娘が話しかけてくれるとつい小言を言ってしまい、会話を中断させてしまうことが多々ありました。例えば、娘が「宿題を忘れた」と言えば、「何で忘れたの?」「帰ったらすぐにやりなさいと言ったでしょ」と、忘れたことに口うるさく反応していたため、娘は不機嫌になりそこで会話が終了するという具合です。
2024年09月23日(月)
No.692
(日記)
子育ては親育て
奈良の清瀬です。
私も、藤岡さんのように、なんで?!と思う子どもの行動や考え方にエニアグラムの学びが救いでした。
長男が生まれた時から育てにくいと感じつつ、必死で育てていました。
何を考えているかわからない、思うように動いてくれない、すぐ泣く。
イライラして、怒鳴りつけることも、手を上げることもありました。
エニアグラムの学びで子どものことがわかるようにはなってきましたが、自分の気質から子どもへの口出しを止めるのが非常に難しかったです。
2024年09月16日(月)
No.691
(日記)
みんな違って、みんないい
愛知の藤岡です。
和木さんの「9歳の大冒険」を読んで、「任せて、見守り、信じる」ことで成長し自信が育っていくお子さんとお母さんの様子に、子どもが中学の頃のことが思い浮かんできました。
中学1年の1回目か2回目のテスト前のことです。
学習方法を教えなくては…という思いで、「テスト勉強はこうやるんだよ。やりなさいね」と私から子どもにひと通りを伝えたとき、
子どもは「そんなこと言うけど、自分はお母さんじゃないから、同じようにはできないよ!」と強く反発したのです。
私は、
(あなたのために良かれと思って伝えているのに…。わかってない!)
とイラッとする反面で、
(親から押しつけられたら、反発するか…、思春期だし。それに、確かに、私とこの子は同じではなさそう。私の伝えたやり方は自己流で、この子にとってのベストではないのかも…)
とも思いました。
その後は、親からの押しつけは意識して減らしていきました。
押しつけなければ、子どもはそう反発することはなく、落ち着いているようでした。
後日、このできごとを改めて振り返る機会になったのが、「エニアグラム」です。
ハートフルコミュニケーションで 書籍と講座があり、「人が生まれ持つそれぞれの気質(全9タイプ)の特徴を学んで、自分を理解し、子どもや身近な人を理解して、接し方のヒントを見つけよう」という内容です。
何か人間関係のヒントが見つかりそう…と興味を持って受講しました。
そこでわかったのは、
「気質のタイプが違う人は、もののとらえ方や考え方、行動もこんなに違うんだ!」
ということでした。
9タイプの気質の特徴について”トリセツ”を手にしたような感覚でした。
2024年09月09日(月)
No.690
(日記)
9歳の大冒険
こんにちは。広島の和木です。
功刀さんと同じく、我が家にも夏休み満喫中の子どもがいますが、普段より一緒にいる時間が長い分、不可侵条約の違反をしていないだろうかと、改めて考えるきっかけになりました。
今年の夏、娘は大きな冒険をしました。というのも、私と二人でパパの実家に帰省しただけなのですが、飛行機に乗り、海を越えてタイのバンコクまで。2歳まで住んでいましたが、その時の記憶はきっとなくて、彼女にとっては初めての海外のようなものです。パスポートの更新やスーツケースの購入、おみやげなど、ワクワクしながら準備を進めました。
準備もそうですし、現地に着いてからのこともたくさん計画しました。色々な計画を立てながら、私がひそかに思っていたことは、この旅は「任せて、見守り、信じる」のスタンスを貫く!ということでした。
この格言、ハートフルコーチになるための講座で先生が教えてくださったもの。子どもの自立のために、子どもに任せて、それを見守り、信じる、という姿勢を学びました。
ところで、この「信じる」は誰のことを信じると思いますか?
「『私』を信じるんです。子どもは、信じて任せても平気で裏切ってくるので、それを自分は見守り続けられると信じてください。」と言う言葉に納得しすぎて爆笑です。座右の銘と言っても過言ではないほど、大好きな言葉です。
話は戻りますが、なぜこの「任せて、見守り、信じる」のスタンスを貫こうと思ったのか。そこには、自分の力でチャレンジして、自信に繋げてほしいという思いがありました。そして私自身も、見守り続けられるよう練習したいとも思っていました。
子どもに任せて、それを見守るところまではできるんです。けれど、見守っているときに娘が失敗してしまったり、間違えたり、困った状況になってしまった時、日本ではない場所であればなおさら、自分が代わりにしようとしたり、前のめりで手伝ったりしそうで…。そうすれば、事は簡単に済みますが、娘が自分で何かにチャレンジする機会を奪ってしまいます。
前回の日記でも書きましたが、幼少期の娘には手をかけすぎていて、その時の後遺症が時々顔を出します。何かするときに「これやってもいい?」「これでいい?」と確認を取って来たり、何かしら私の顔色を伺うことがあるんです。気の小ささや恥ずかしがりな性格も相まってはいますが、「これやってもいい?」と訊かれる度、なんだかごめん…と思ってしまいます。
2024年09月02日(月)
No.689
(日記)
余計な口出しをしないために
こんにちわ、東京の㓛刀です。
菅原さんのように私も子供に手伝ってもらう時、素直に言葉にすることを心がけ、そして感謝の心を伝えようとあらためて思いました。
さて、この日記を書いている今日は8月19日。7月25日に始まった高2の息子の夏休みも残すところ2週間となりました。この夏、我が家は旅行の計画も息子が所属する軽音部の活動もなく、塾の夏期講習も申し込まなかったので、約6週間の自由な時間がそっくり息子に与えられたことになります。
夏休みが始まる少し前、確か息子は「夏休みの計画を立てた」と言っていました。ところがいざ夏休みが始まると昼までベッドでゴロゴロ、ゆっくり起きてからランチを食べ、そのあとはソファにひっくり返って音楽を聴いたりスマホを見ているだけです。1週間経っても机の上の参考書は1ミリも動きません。
2024年08月26日(月)
No.688
(日記)
「お手伝い」と「人の役にたつ喜び」
東京の菅原典子です。
二人の子どもも大きくなり、子育てもあと少しといったところの我が家ですが、もっと家のことを手伝って欲しいと願うものの、こちらも満足のいくようにはなかなかやってくれずに日々試行錯誤しています。今回は子どもの「お手伝い」について、あれこれ考えたことを書きたいと思います。
大学・高校生になった子どもたち。お昼ご飯も勝手にやってくれるし、私が仕事で帰りが遅くなっても心配の要..
2024年08月19日(月)
No.687
(日記)